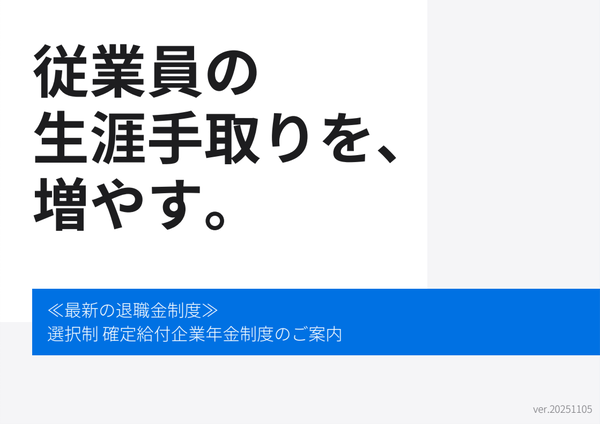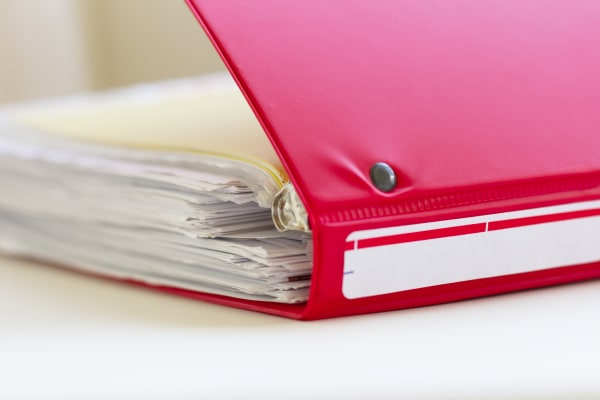退職金制度と資産形成支援の種類・特徴(メリット・デメリット比較)
中小企業において、退職金制度は人材定着・採用力強化のカギです。さらに近年は、従業員の資産形成を支援するiDeCo+やNISAといった制度も注目を集めています。
ここでは、主要制度の特徴・メリット・デメリットを比較し、導入検討の参考となる情報をまとめます。
制度比較一覧表
| 制度名 | 外部積立 | 損金扱い | 社会保険対象外 | 導入難易度 | 従業員満足度 | 柔軟性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職一時金 | ― | △ | ○ | |||
| 中退共 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| DB年金 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| DC年金 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| iDeCo+ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| NISA | 個人口座 | ― | ― |
1. 退職一時金制度
特徴
退職時に企業が一括で退職金を支給する制度。社内管理型で、就業規則に定めるだけで導入可能。
メリット
- 制度設計の自由度が高い
- 導入コストが低い
- 勤続年数や退職理由に応じて柔軟に支給可能
デメリット
- 資金を社内で確保する必要あり
- 退職が重なると資金繰りに影響
- 税制優遇が限定的
2. 中小企業退職金共済制度(中退共)
特徴
国が運営する共済制度で、掛金を外部に積み立てる形式。安全性が高く管理負担も少ない。
メリット
- 掛金全額が損金算入可能
- 社会保険料の対象外
- 国の助成金制度あり(加入初年度)
デメリット
- 掛金額の変更が柔軟でない
- 制度変更や解約に制限がある
- 個別設計の自由度が低い
3. 確定給付企業年金(DB)
特徴
将来の給付額を企業が保証する制度。安定性が高く、大企業を中心に普及。
メリット
- 従業員の安心感・満足度が高い
- 税制優遇を受けられる
- 長期雇用の促進効果
デメリット
- 導入・維持コストが高い
- 運用リスクは企業負担
- 専門知識と事務負担が必要
4. 企業型確定拠出年金(DC)
特徴
企業が掛金を拠出し、従業員が運用先を選択。投資成果によって将来の受取額が変動。
メリット
- 社会保険料の負担軽減
- 税制優遇が大きい
- 経営者自身も加入可能
デメリット
- 投資知識が必要
- 成果に個人差が出やすい
- 制度設計・維持に手間がかかる
5. iDeCo+(イデコプラス)
特徴
中小企業の従業員が加入しているiDeCoに対して、企業が掛金を上乗せできる制度(従業員300人以下が対象)。
メリット
- 導入が簡単でコストも抑えやすい
- 掛金は全額損金扱い・社会保険料対象外
- 中小企業の福利厚生強化に効果的
デメリット
- 加入対象は「iDeCo加入者」に限られる
- 上乗せ掛金の上限が低い
- 制度の認知度がまだ低い
6. NISA(新NISA)
特徴
個人の投資による運用益が非課税となる制度。退職金制度ではないが、企業が金融教育や投資支援制度として取り入れる事例が増加中。
メリット
- 少額から投資が可能
- 運用益が非課税で老後資金形成に有効
- 福利厚生の差別化に繋がる
デメリット
- 企業が直接掛金拠出は不可
- 成果は自己責任
- 投資リスクの理解が必要
当事務所の退職金コンサルティングの強み
- 社労士ならではの就業規則との整合性確認
- 企業のニーズに応える最適な制度を選択
- 吹田市・大阪府内で多数の導入実績
- 制度の導入・運用までワンストップ支援
導入の流れ
初回無料相談(現状ヒアリング)
制度の設計・比較提案
社内説明・就業規則改定支援
制度導入
退職金制度は「人材定着」のカギ

採用活動において福利厚生は重要な要素

特に中小企業は「退職金制度」の有無で競争力に差

若手~ベテラン社員まで安心して働ける環境づくりに
よくある質問
A. 貴社の業種・従業員数・財務状況を踏まえ、最適な制度をご提案します。
A. はい、既存制度の課題点を分析し、改善策をご提案します。
A. 退職金制度の導入は法律上の義務ではありません。しかし導入することで、従業員の定着率向上や採用活動における大きなアピールポイントとなります。
A. 業種や規模によって異なりますが、中小企業の場合、勤続30年で500万~1,000万円程度が目安とされます。ただし、会社の財務状況を踏まえて無理のない制度設計を行うことが重要です。
A. 退職金制度を導入する場合は、就業規則や退職金規程に明記することが必須です。支給条件や計算方法を明確にすることで、労使間のトラブルを防ぐことができます。
A. 正社員のみを対象にしたり、勤続年数や勤務態度によって支給額を変える設計も可能です。ただし、不合理な差別的取扱いは避けなければなりません。
A. 可能ですが、労働条件の不利益変更にあたるため、従業員への十分な説明と同意、または代替措置が必要です。
A. 退職金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。そのため、通常の給与所得よりも税負担が軽くなります。
A. 職金の積立に充てる会社の掛金(積立金)については、原則として社会保険料の対象にはなりません。
社会保険料は「労働者へ実際に支払われる賃金」に対して課されるものであり、将来支給される退職金のために会社が積み立てる掛金は、現時点で従業員に帰属するものではないからです。
ただし、退職金を給与として前払いする形にした場合や、制度設計上「賃金」とみなされる運用を行った場合には、社会保険料の対象となる可能性があります。そのため、積立方法や制度設計の段階で社会保険労務士など専門家に確認することが重要です。
A. はい、あります。退職金に対する考え方は、会社によって違いますので、御社にとって最適な制度をご提案しますので、共に構築して参りましょう。
A. 導入時に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 財務的に無理のない設計になっているか
- 公平性が保たれているか
- 将来の見直しや法改正に対応できるか
これらを意識し、制度設計の段階で専門家へ相談することをおすすめします。
A. 助成金制度は、年度ごとに改変されますので確実ではありませんが、退職金制度導入を支援する助成金が発表されることがあります。人事制度の改善や企業年金関連の施策に関連する助成金を利用できる可能性があります。厚生労働省や社労士へ確認すると良いでしょう。
まずはお気軽にご相談ください
- 「退職金制度を整えたい」
- 「福利厚生で社員を定着させたい」
そんな企業様は、今すぐご相談ください。
早めに社会保険労務士に相談すること、
これが一番の解決方法です。
労務トラブル・終了規則作成・給与賃金制度など人に関する相談は無料です。
まずはお気軽にご連絡ください。